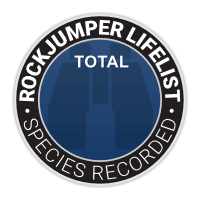絶滅は自然現象ですが、専門家によると、現在の鳥類の絶滅率は背景絶滅率の1,000倍から10,000倍の間です。過去500年間で150種以上の鳥類が絶滅したことが知られており、さらに多くの種が科学に知られるようになる前に絶滅に追い込まれたと推定されています。近年の鳥類の絶滅の大部分は島嶼部で発生しており、島嶼部では生息範囲が狭く、個体数も少なく、外来捕食者への適応が不十分なため、種が絶滅の影響を受けやすい状況にあります。アフリカを除くすべての有人大陸で鳥類の絶滅が発生していますが、2012年に更新されたIUCNレッドリストでは、絶滅の危機に瀕する鳥類がますます増えているという、驚くべき、しかし全く予想外ではない傾向が示されています。.

2011年以降、絶滅危惧IA類(絶滅の危険性が極めて高い)のリストは189種から197種に、絶滅危惧IB類(絶滅の危険性が非常に高い)のリストは381種から389種に増加しました。世界的には、総数10,064種の鳥類のうち1,313種が絶滅の危機に瀕しており、これは全体の13%という恐ろしい数字です。人類の進化の時代から鳥類が人間と共存してきたアフリカでさえ、ますます多くの鳥類が絶滅危惧種の仲間入りをしています。絶滅危惧IB類に新たに追加された種には、威厳のあるハイイロカンムリヅル(危急II類から一つ上のカテゴリーに)、そしてわずか1年で準絶滅危惧IB類から二つ上のカテゴリーに飛び上がったミミナグサハゲワシとオジロハゲワシが含まれます。.

現在、絶滅危惧または深刻な絶滅危惧に指定されているアフリカの鳥類 115 種のうち、ほぼ半数はアフリカ周辺の島々に生息しているか、繁殖期以外でアフリカに渡来しています。このブログ投稿では、アフリカ大陸に生息する絶滅危惧種 60 種のうち 10 種について説明します。これらの種は必ずしもアフリカで最も希少な種というわけではなく、実際には現在も大量に生息している種もいますが、IUCN レッドリストに掲載されたのは、これらの種の過去 3 繁殖世代にわたる急速な個体数の減少によるものです。この 10 種が選ばれた理由は、アフリカの鳥類が絶滅に追いやられている無数の理由の一部を示すためです。その理由には、商業目的の乱獲、送電線との衝突、違法取引、中毒、伝統薬の使用、過放牧、特殊な生息地の農地への転換などがあります。.

オオカンムリヅル
独特の金色の羽飾りを持つ、世界で最も印象的な鳥類の一つであるこの堂々とした種は、世界中でよく知られています。アフリカで真に爽快な体験の一つは、湿地帯の早朝の霧の中から現れ、近くに降り立ち、羽ばたきやジャンプのディスプレイを始めるこの巨大な鳥の群れの鳴き声を、見聞きすることです。ハイイロカンムリヅルは南部および東部アフリカのほとんどの地域に生息していますが、その個体数は過去19年間で50%以上減少したと推定されています。この種は湿地帯を好み、人口増加による生息地の破壊と、ペットや動物園取引のために野生の鳥や卵を違法に持ち去ることによって、その数は激減しています。.



ルッペルハゲワシ、シロハラハゲワシ、フサハラハゲワシ
アジアでハゲワシの数が劇的に減少した後(ジクロフェナクという主に牛の治療に使われる獣医薬でハゲワシには致命的であるものの影響で、数年で数種のハゲワシの個体数が 99% 以上も減少した)、アフリカのハゲワシも今や絶滅の危機に直面している。前述のように、ミミナグサハゲワシとシロハラハゲワシは絶滅危惧種のリストに新たに追加されたが、シラハゲワシは何年も前からリストに載っている。興味深いのは、これら 3 種のハゲワシは実際には数的に最も一般的で、獲物や他の食料源で最も頻繁に遭遇するハゲワシであるにもかかわらず、個体数の減少が最も大きく、絶滅のリスクが最も高い種だということ。ミミヒダハゲワシ、シロガオハゲワシ、ケープハゲワシなどの他の希少なハゲワシは、いずれも脅威度は低いが、生息数ははるかに少ない。シラハゲワシとオオハゲワシはサハラ以南のアフリカのほぼ全域に生息していますが、ルッペルハゲワシは東アフリカと西アフリカにのみ生息しています。これらのハゲワシは、生息地の喪失(主にサバンナの農地化)、直接的な迫害、無差別な毒殺、そして餌の大部分を占める野生有蹄類の個体数の減少により、急速な個体数減少を経験しています。南アフリカと西アフリカでは、伝統医学のためにハゲワシが殺されることもあります。例えば、一部の文化ではハゲワシが未来を予言できると信じられており、宝くじの当選番号を正確に予測するのに役立つとされ、ハゲワシの体の一部が購入されることもあります。

北ハゲトキ
ホオジロトキは、IUCNレッドリストによって現存する野生種に割り当てられた最高リスクカテゴリーである絶滅危惧IA類に分類されています。ホオジロトキは、1504年にザルツブルク大司教レオンハルトの勅令により、最も早く公式に保護された種の一つであったにもかかわらずです。この奇妙だが美しい羽毛を持つ鳥は、ヴァルドラップ(「森のカラス」の意)としてヨーロッパ中で広く知られていました。南ヨーロッパと中央ヨーロッパの崖や城の城壁で大規模なコロニーで繁殖していましたが、絶滅に向かって容赦ない行進を開始しました。18世紀までにはヨーロッパ全土から姿を消し、中東でもこのパターンが続き、最終的にはトルコた。このコロニーは、トキが毎年メッカへのハッジ巡礼者を導くために移動するという地元の宗教的信仰によって保護されていたため、他の数十のコロニーよりも長生きしました。 1930年代にはビレジクで約3,000羽の鳥が夏を過ごし繁殖していましたが、1982年までに400羽にまで減少しました。1986年までに野生のつがいは5つがいにまで残り、1990年には1羽にまで減り、その鳥も翌年に死んでしまいました。ホオジロトキは北アフリカにも生息し、モロッコとアルジェリアが、この悲劇的なパターンは続き、アルジェリアの最後のコロニーは1980年代に姿を消しました。モロッコでは1940年に38コロニー、1975年に15コロニーが残り、1989年にはアトラス山脈にいた最後の渡り個体が絶滅し、1990年代まで残っていたのはモロッコ沿岸の2か所にある4つの繁殖コロニーで、繁殖つがいは合計56つがいでした。ワルドラップ種の個体数は、集中的な保護活動にもかかわらず、減少し続けました。

餌場の喪失、巣の撹乱、狩猟、毒殺などにより、絶滅は避けられないと思われました。しかし、この脆弱で悲劇的な状況は、バードライフ・インターナショナルやその他の保護団体による集中的な保護活動により改善されてきました。モロッコのコロニーでは繁殖個体数が増加しており、現在では繁殖つがい106組、総数約500羽と推定されています。そして2002年には、70年前に絶滅したとされていたシリアのパルミラで、残存コロニーが劇的に発見されるというニュースが、歓喜をもって迎えられました。悲しいことに、この中東にわずかに残された個体は、発見時の7羽から、今年巣のコロニーに戻ったのはわずか3羽にまで減少しています。これらの鳥には標識が付けられ、冬を過ごすエチオピア高原のスルルタ平原へと渡ります。興味深いことに、さらに2羽の若い鳥も今シーズンこの地域で越冬したが、これら2羽の重要な鳥の起源は未だ解明されていない謎である。.
トルコのビレジクには、約100羽の半飼育個体群が現在も生息しています(繁殖期の5ヶ月間は放鳥され、その後、渡り・越冬期は飼育下で飼育されています)。スペインとオーストリアにも小規模な半飼育個体群が存在し、シリアではビレジク個体群の再導入プログラムが開始されています。.

アフリカペンギン
ジャッカス(その鳴き声から)またはクロアシペンギンとも呼ばれるアフリカ唯一のペンギンは、大陸の涼しい南部にのみ生息し、南アフリカとナミビアの沖合25か所と本土4か所のコロニーで繁殖しています。個体数は過去3世代で61%減少したと推定されており、その主な原因は、トロール船による商業的な乱獲による食糧不足と、好む魚種の個体数と分布域の変動です。このペンギンの目撃情報が最も多いのは、ケープタウンのすぐ南、サイモンズタウン近郊のボルダーズビーチで、毎年何万人もの観光客がペンギンを見に訪れます。興味深いことに、このコロニーは1980年代に設立されたばかりで、現在ではアフリカペンギンの個体数の80%以上を支える7つの重要なコロニーの1つとなっています。ここではペンギンを簡単に観察でき、フェンスで囲まれた巣作りエリアと歩行者用の遊歩道でしっかりと保護されているため、訪問者がペンギンに迷惑をかけることはほとんどありません。ただし、駐車場を出る前に、車のタイヤの下にペンギンがいないか必ず確認してください……

ルートヴィヒノガン
南アフリカ西部、ナミビアアンゴラ南部にまでいます。遊牧民であり、個体数は20年間調査されていませんが、南アフリカでは主に送電線への衝突により、個体数が51%減少したと推定されています。これは、特に大型で長寿のノガンにとって壊滅的な打撃であり、南アフリカとナミビアにおけるインフラ開発のさらなる進展は、この問題をさらに悪化させるだけです。生息地の破壊、狩猟、撹乱も個体数に影響を与える要因です。送電線へのマーキング実験が複数実施されており、この種を悩ませている主な問題に対する有効な解決策が見つかることが期待されています。

リベン・ラーク
以前はシダモラークと呼ばれ、現在ではエチオピアで、生息数は250頭未満と推定され、面積はわずか30~36平方キロメートルです。この平原はかつては人間の影響をほとんど受けておらず、わずかな牛、ヤギ、ラクダが放牧されているだけでした。しかし、ここ数年で民族紛争や干ばつにより周辺地域から追い出された何千人もの人々がこの地域に移住してきたため、状況は変わりました。近年の人間の活動の大幅な増加により、未開の草原の大部分が耕作され、残りの地域では深刻な過放牧が起きています。この過放牧と、草原の健康と活力に不可欠な野火の制限は、さらに灌木侵入やその他の生息地の大幅な変更をもたらしています。 2007年から2009年の間に、リベンヒバリの個体数は40%減少し、生息域も38%縮小しました。アフリカ大陸で初めて絶滅した鳥類である可能性が指摘されており、科学者たちは、大規模な保護活動が行われない限り、あと2~3年しか絶滅の見込みがないと推定しています。しかし、2011年1月にロックジャンパーのツアーに参加したデビッド・ホディノット氏が、エチオピア北東部ジジガ近郊で、類似のヒバリの個体群を発見したことで、リベンヒバリの別の個体群が存在する可能性が浮上しました。あるいは、デビッド氏が発見した鳥は新種である可能性もあれば、1922年以来確認されていない近縁種のアーチャーヒバリの分布域拡大である可能性もあります。この新個体群に関する詳細な考察と画像は、こちらのブログ記事をご覧ください:https://www.rockjumperbirding.blogspot.com/2011/05/significant-ethiopian-discovery.html

ボタのラーク
この小型で、どちらかといえば地味なピンク色の嘴を持つヒバリは、南アフリカ中東部の高地草原に固有の鳥です。生息域の80%以上は農業の影響で既に変化しており、残存個体数(推定1,000~5,000羽)に対する脅威としては、さらなる耕作、商業植林、鉱業などが挙げられます。限られた生息域内では、過放牧で乾燥した草原を好むようで、繁殖の成功率は草原の焼却時期によっても悪影響を受ける可能性があります。非繁殖期におけるボタヒバリの行動についてはほとんど分かっていません。.

シャープのロングクロー
ケニア固有種で、高地の草地が農地化されていない、わずかに残る断片化され孤立した地域に生息しています。ケニアでは、人口増加と小規模農家による自然草原の転換が本種に壊滅的な影響を与え、個体数の大幅な減少を引き起こしています。残存個体数は2,000羽程度と推定されており、大規模な草地が保全されない限り、本種は絶滅の危機に瀕しています。